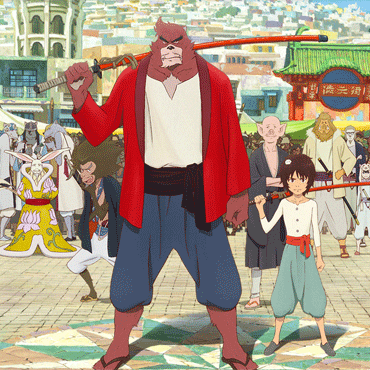立川シネマシティで細田守監督の『バケモノの子』を観ました。細田監督の作品を観るのは、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』に続いて4作品目です。
細田作品に共通しているのは、ファンタジーと現実世界の融合にあると思います。現実と完全に切り離されたファンタジーではなく、現実と接点を持ったファンタジーを志向しているのではないかと。今回の作品もこれまでの作品同様、もしくはそれ以上にこの特徴が現れていました。
では、まず本作のあらすじの紹介から。
目次
『バケモノの子』あらすじ
渋谷の街に生きる孤独な少年・蓮は、ある日、熊徹という名のバケモノと出会う。熊徹の姿に恐ろしさを感じながらも、独りで生きていく強さを手に入れるため、蓮は彼の後を追う。いつしかバケモノの世界「渋天街」に迷い込んでしまった蓮は、そこで熊徹に弟子入りし、熊徹から九太と命名される。熊徹との修行の中で九太は成長し、バケモノの世界でも一目置かれる存在に。17歳になったある日、渋谷へ戻った九太は楓という名の高校生の少女と出会う。蓮は楓から学ぶことの喜びを教えられ、自分が進むべき道を模索するようになる。そんな中、交わるはずのない人間界「渋谷」とバケモノ界「渋天街」の両世界を巻き込む事件が起こり・・・。
『バケモノの子』キャスト紹介
主人公の一人で、渋天街で一、二の強さを誇るバケモノ・熊徹の声を役所広司、もう一人の主人公、九太(蓮)の声を宮崎あおい(少年期)と染谷将太(青年期)の二人が演じています。宮崎あおいは、『おおかみこどもの雨と雪』でも主人公の花の声を演じていましたね。
その他、熊徹の友人でサル顔のバケモノ多々良役に大泉洋、聡明なバケモノの僧侶・百秋坊役にリリー・フランキー、17歳になった九太が出会う高校生・楓役に広瀬すず、熊徹のライバル猪王山の息子で九太と対決する一郎彦役に黒木華と、声優を本職としていない俳優の面々がキャスティングされています。
スポンサーリンク
感想(ネタバレ含む)~ファンタジーと現実の往復
細田守監督の特徴は、現実世界とファンタジーの世界を融合させる作風にあると思います。今作ではさらにその特徴が際立っていて、主人公の九太は人間の世界である「渋谷」とバケモノの世界である「渋天街」を何度も行き来します。物語自体が、現実とファンタジーを並列させ、往復させる構造になっています。
現実の世界から異世界に迷い込み、物語が始まるというのは多くのフィクションに見られる傾向ですが(『不思議の国のアリス』、『千と千尋の神隠し』等々)、今作の主人公は二つの世界を何度も往復します。熊徹に弟子入りし修行に励む九太と共に、動物の角や牙を持つバケモノ達が暮らす『渋天街』に身を置いた観客は、突如としてリアルな渋谷の街に引き戻されます。しかも九太は、図書館で出会った高校生・楓に大学受験を勧められ、共に役所に行って高卒認定試験(旧大検)の説明を受けたりします。「渋天街」という非現実的な世界での生活と、大学受験というモロに現実的な要素が一つの作品内に共存しているんです。下手すると荒唐無稽なほら話と感じさせるところを、しかし細田監督は力技で作品として成立させてしまっています。このような突飛な世界観を観客にリアルなものとして感じさせるのは非常に難しいのですが、彼は前作『おおかみこどもの雨と雪』でも同じような試みをしていました。
『おおかみこどもの雨と雪』は、オオカミ男との間に二人の子を授かった女性「花」を主人公とした母と子の物語です。花が生きる世界は私たちが生きる普通の世界で、物語の冒頭で彼女は大学に通っています。この作品で現実離れしているのは、花が恋したオオカミ男の存在と、彼との間に生まれた人間・オオカミ両方の血を受け継ぎ、自在にその姿を変えることのできる二人の子ども「雨」と「雪」の存在だけです。オオカミ男と人間の間に生まれた子どもの話なんて、その設定だけ聞いたら普通バカバカしくて見る気になりません。有名な童話とかならまだしも、オリジナルの作品ですし。しかしこの作品は興ざめしてもおかしくないこのような設定の物語が、子の成長を見守る母の気持ちや、自分が何者であるかということに迷う思春期の少年少女の気持ちを最低限のリアリティを持って表現できています(母性礼賛的な描き方や少女の成長の仕方には強い違和感を覚えましたが)。
荒唐無稽な話をもっともらしく見せることは、作品自体に独自のリアリティを与えるために必要なことです。絵の力はもちろん、登場人物の心理の機微を表現する脚本と演出の上手さ、声優の演技力等、複合的な要素がそのリアリティを支えます。
現実の社会を描いていようがアニメーションがフィクションであることに違いはないのですが、『バケモノの子』では、店の看板などの細かい所まで忠実に再現された渋谷の街が舞台となっており、これまでの作品以上に現実に寄っています。一方で、バケモノが暮らす「渋天街」のようなファンタジー全開の世界はこれまでの細田作品には出てきませんでした。つまり、より現実的な世界とより虚構的な世界を並列させているわけです。ファンタジーと現実世界の融合という点で、細田監督は『バケモノの子』において、前作以上に難しいことに挑戦しています。
普通、ドランゴンボールの天下一武道会のような場面(熊徹と猪王山の格闘シーン)と、リアルな渋谷のスクランブル交差点の映像を同じ作品内で見せられたらそのギャップに戸惑うものです。実際に私も最初の方は中々作品に入り込めなかったのですが、物語が進むにつれて違和感は失われ二つの世界は融合し、長編アニメーション作品としてちゃんと成立しているように思いました。さすがにラストで主人公が大学受験を決意する場面は、超大掛かりなZ会のCMかよ!ってツッコみたくなりましたけど(笑)
ちなみに細田監督は、「今の時代にファンタジーを作ることはできない」と言って『風立ちぬ』を制作した宮崎駿や、その宮崎駿作品に対して「余りに良く出来ているために観客がファンタジー漬けになってしまう危険性」に警鐘を鳴らした高畑勲の影響を強く受けています。細田作品の特徴である、現実と繋がりを持ったファンタジーというのは、「現実とファンタジーの関係性」という、高畑・宮崎が長年考えてきた主題を細田守も共有していたことの証左であると思います。
参照サイト:弁証法的な緊張関係-高畑勲と宮崎駿の50年-

テーマは「新しい家族像」と「他者からの承認」
本作はテーマが明確だと感じました。まあ作品のテーマなんて観客が自由に解釈するものなので正解なんてないと思いますが、私は「新しい家族像」と「他者からの承認」が本作のテーマだと思います。
母親が死に、父親から捨てられたと感じている九太(蓮)は、師匠の熊徹や多々良、百秋坊たちに見守られ、迷いながらも自己を確立していきます。両親の存在がなくても、一人の人間としての成長が可能であることをこの作品は示そうとしています。父親がいて、母親がいて、という旧来の家族観とは異なる家族の形の提示です。
それでは本作における家族とはどういったものなのでしょうか。細田監督は家族を「無条件に自分の存在を承認してくれる相手」として描いているように思います。映画の序盤、周囲への憎しみを増大させた九太の身体には黒い大きな穴が開きます。この穴は、「自己肯定感の欠乏」と捉えることができます。熊徹をはじめとするバケモノたちと暮らす中で、九太は他者からの承認を獲得し、欠乏感は解消されます。これは、父親でも母親でもない周囲の大人たち(バケモノたち)が九太にとっての家族になったということを意味します。
ラストで九太と対決する一郎彦も、バケモノの子として育てられながら人間であることに悩み続けた挙句、憎しみを募らせ、身体に大きな穴ができてしまいます。一郎彦は血の繋がりのない両親と弟からの承認によって穴を埋めます。映画の終盤に、九太との対決の後、ベッドで目を覚ました一郎彦のそばで両親と弟が寝ずの看病の末に眠りこけるという象徴的な場面があります。これは、血の繋がった子ども(弟の二郎丸)と血の繋がっていない子ども(一郎彦)が同居する家族という、大昔から存在しているにも関わらず、日本におけるスタンダードな家族像からは逸脱していると見なされてきた家族の形の肯定と捉えることができます。
ちなみに、細田守監督自身は、本作についてインタビューで以下のように語っています。
今回考えたのは「子どもがこの世の中で、どうやって成長して大きくなっていくのだろう」ということ。自分自身が親となって実感したことでもあるのですが、子どもというのは親が育てているようでいて、実はあまりそうではなく、もっと沢山の人に育てられているのではないかなという気がするのです。父親のことなんか忘れて、心の師匠みたいな人が現れて、その人の存在が大きくなっていくだろう。そうしたら、父親、つまり私のことなんて忘れちゃうかもしれない(笑)。それが微笑ましいというか、それぐらい誇らしい成長を遂げてくれたら嬉しいなということを自分の子どもに対して思うのです。子どもが沢山の人から影響を受けて成長していく様を、この映画を通して考えていきたいです。そういう映画はあるようでないと思うので、そこが凄くチャレンジではないかと思います。
引用元:細田守監督インタビュー
映画の感想からは離れてしまいますが、このインタビューを読むと、「子どもを教育しなきゃ」という、子どもの立場からすると鬱陶しい親の前のめり感を否定している点では共感できます。一方で、父親というか子の保護者としての責任放棄、エクスキューズのようにも聞こえてきます。子育ての現場における父親の不在が問題となっている日本社会だからこそ、尚更そう感じてしまいます。放っておいても子は育ちません。というか、乳幼児であれば放っておいたら子は死にます。何もしなくて育つと思えるのは、その人の気づかないところできちんと子どもをケアしてくれている人(多くは母親)がいるからです。日本の父親はもっと保護者としてのケア責任を果たさなければならないという自覚を持つべきでしょう。「子は親がいなくても育つ」などと言っている場合ではなく。もしかすると細田監督が言う子育ては「人生の教訓を説いて聞かせる」といった説教臭いものを想定しているのかもしれないので、私の捉え方と齟齬があるのかもしれませんが。
スポンサーリンク
テーマの明確さが作品の広がりを阻んでいる
前述しましたが、『バケモノの子』はテーマが作品内でかなり明確に表現されていると思います。観客にメッセージを伝えようという意図が強く、それは親切で分かりやすいと言える一方で、作品の解釈の幅を狭めているようにも感じました。分かりやすさというのは一概に否定されるべきものではないと思いますが、映画を観終わった後の印象として、映像やイメージよりも作品全体のメッセージ(言語化できるもの)の方が強く残る気がしました。余韻がないというか、観客の想像力で埋める余白が少ないというか。まあこの辺はかなり主観的な印象になってしまいますけどね。
例えば渋谷のスクランブル交差点の下を鯨が泳ぐ場面はその発想も含めて素晴らしかったですし、鯨と化した一郎彦と九太が戦う映像は迫力があり、美しくもありました。そもそもなぜ鯨かというと、これは九太(楓だったかも)が道端に落としたハーマン・メルヴィルの『白鯨』を一郎彦が目にしたからです。つまり偶然です。もちろん、作品内で鯨は象徴性を帯びていますが、物語上はふとした偶然から一郎彦が鯨の姿に化けるという展開になっています。このさりげなさが、メッセージ性が強く、作家の作為が透けて見える本作の中において、際立って良かったと思います。
本作は、細田守監督自身が脚本を担当しているそうです。私が抱いた「メッセージ性が強い」という印象はこの辺りにあるのかもしれません。同時に、『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』で脚本を担当した奥寺佐渡子の存在は、やっぱり大きかったんだなとも思いました。
「金曜ロードSHOW!」で「バケモノの子」が放送されます
2016年7月22日(金)、日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」で『バケモノの子』が地上波で初放送されます。夏休みの時期の「金曜ロードSHOW!」と言えば「ジブリ」でしたが、ここ数年、細田守作品も多く放送されるようになりました。
本編ノーカットでの放送で、放送時間は25分拡大となります。
※放送は終了しています。
放送日:2016年7月22日(金)
放送時間:21:00~23:19
私も久しぶりに見直してみたいと思います。また違った感想を持つかもしれません。
【追記】
2018年7月27日、金曜ロードショーで再び『バケモノの子』が放送されました。
どうでもいいことかもしれませんが、私はこの記事を書いた当時と比べて今ではかなり細田作品に対して否定的な印象を持っています。特に家族の描き方、女性の描き方に多くの問題があると考えています。
スポンサーリンク